

| 11/30(金) | 直腸炎 proctitis 2週間ほど前からひどい下痢と血便があって、いろいろ 下痢について - 愛知県薬剤師会生活科学センター医薬品情報部米島隆一室長 |
| 10/26(金) | 考え事をしたいときはいつも邪魔がはいる。そしてきちんと消化しきらない言い訳になってしまう。いつの間にか役にはまって persona(ペルソナ)をつけている自分がいる。言葉に表れるのは、決して嘘ではなくて、でも本当でもなくて。まったくもって全然違う景色だという認識に嫌気と羞恥心がわき起こって、それを眺めることもきちんと積み上げておくことも出来ずに、自ら招いた煩瑣な仕事が隣に山積みになっていくだけなんていう笑えない話。いつの間にか忘れていた振り返ること。別に後ろを見ることじゃなくて、例えば今自分がどんな服を着ているんだろうなんてことや自分の性格。いつだって気にしてるぐらいでちょうど良いのかもしれない。結局は、自分っていう存在と、他のものの存在の差、それはいろんな価値だったりそのほかのものだったりするけれど、普通に成人が生きていく上で即自的な(それが本来のスペックのままそれ自身充足している、自分自身においての)自分というものは現実的にはありえなくて、どうあがいても対他的で相対的なあり方をとらざるを得ないのではないかと思う。そういった各々の存在の差を感じたとき(「差異」の中に迷い込んだとき、とでも言おうか)、限界状況とでも言うような切迫感が生まれて、口惜しいけれど、顔を上げて前を見なきゃいけなくなる。対自的なあり方までたどり着けないならず者のまま。答えはいつも用意されているはずだと思う。でもいつもそこから目をそらしているだけで、しかもそのことにまったく合理的な意味がなかったり、思いっきり逆走してることの方が多いのだろう。おそらくはあまりに脆弱すぎる哀れな自我による、自らの誇大感に対する補償としての自己否定からあふれ出す不安と諦念。それがそれぞれの態度を狂わせる毒となっているのだろうか。自分がそこに居ていい理由。ひとにとって、また自分にとって。そのための価値は当たり前のように見いだせないまま、見いだせる可能性も見つけられないまま、今必要なのはただ笑っていられる強さなんだろうと。必要であるということは、現状では必要であることそれ自身を満たしていない。 |
| 10/24(水) |
無計画性が強いというわけではない。でもなにか落ち着かない。もともと最初から落ち着かない日だった。自分の中で消化しないといけないものが多かったから。それでもはっきりと割り切るほどきちんとした理由でもないから、雑踏の中で現実に翻弄されてしまうことになる。 |
| 10/23(火) | 小坂修平・竹田青嗣 他 『わかりやすいあなたのための現代思想・入門』 見たいものが見られたはずなのに、気分はそんなに踊らないまま。ひとにはキャパシティがあって、煩雑な問題がある程度そこを占めていると、望んだものを十分に感じ取るだけの空きがなくなって、アンニュイが支配するだけなのかもしれない。至らなさすぎる自分の至らなさを考えると諦念で溢れてしまいそうになる。いつかどうでもよくなってしまいそうで。 |
| 10/21(日) | 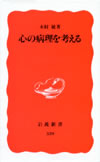 木村敏 『心の病理を考える』 岩波新書 359 1994.11.21.初版 木村敏 『心の病理を考える』 岩波新書 359 1994.11.21.初版『時間と自己』に比べるとずいぶんと人間くささを感じさせてくれる本。10年以上も経っているのだから当然といえば当然か。文章もずいぶんと手慣れてきているようで、以前に比べてかなり読みやすくなっている。木村敏にしては随分と地で書いたようで、その分あとがきも2ページだけ。自他共に認めるナルシシストなんだとか。 第二章の「精神病理学の歩み」は現存在分析の流れを解説している伝記的な内容。手頃に読める現存在分析の歴史といったところか。以前ユング心理学のMLで現存在分析についての入門書を聞いたときに教えてもらった本。 |
| 10/19(金) |  木村敏 『時間と自己』 中公新書 674 1982.11.25.初版 木村敏 『時間と自己』 中公新書 674 1982.11.25.初版実存主義と精神病理学の立場から提出された時間論。時間と自己を切り離せないものとして論じている。衒学趣味な教養志向のひとにはぴったりの一冊。 Ludwdig Binswanger(ルードウィヒ・ビンスワンガー)や Viktor von Weizsacker(ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー)の翻訳も多く手がけている実存思想よりのひとらしい。Martin Heidegger(マルティン・ハイデッガー)の哲学をよく援用している。専攻が精神病理学なだけあって、どういう病気があってどういう特徴かということについて詳しく書いてあることが多い。抽象的な哲学の話が多いので具体的な臨床例に基づいた解説というのはほとんどない。 個人的には絶対「あとがき」から読むことを勧めたい。出だしが日本語のすばらしさをたたえる哲学談義なので、あとがきで著者の雰囲気を先に知っておいて気楽に読んだ方がよさそう。 |
| 10/10(水) | 精神分析には「解釈」という言葉があって、理由のよく分からない行動の背後には無意識的な心の働きがあると考えて、その行動を解釈することで無意識を知ろうとするらしい。言うなれば行動の意味みたいのを考える。人の言動って本人が自覚してなかったりしても、いろんな意味があって。よくわからない言動に、どんな意味があるんだろうって考える。そのことについてよく考えてたら、その意味を見つけようとするだけじゃなくて、そこから意味を新しく作っていけたら、きっと物事がもっと良くなるんだろうな、って思いついた………んだけど、予想以上の自分の存在の無意味さ、無価値さを唐突に思い知らされると、何も分からなくなって、全然がんばれなくなって、黙ってしまう。 |
| 10/1(月) | もう2週間以上本を読んでない。最近少しずつ自分の中の哲学が形作られている気が、なんとなくする。でも哲学や世界観という言葉は、ちょっと違うかもしれない。なんて言えばいいんだろう。精神分析は自我心理学から対象関係論に移ってきたようだけど、自分の中でも、自分に対する考え、みたいなものから、人との関わりの中での自分へ、意識が変わってきたふうに感じる。でも、すべては保留のまま、問題が積み重なっていく感覚に変わりはなくって(実際にそれは当たっていると思う)、がんばらなきゃいけない意識が何度となくわいてきてしまう。無理をしたら違うところでそのつけがまわって出てくると思うし、無理をしなければ何も変わらないとも思う。でも無理をし続けるのは、自分を必要以上に大きく保たなければ維持できないほど不安な心の現れだと思うから、それはなにか違う気がする。それでも、確かに景色が違う風に見えた日があった。 「ならず者」を見つけた。向こう見ずの無法者。特に初期の米国西部の者。スペイン語が語源らしい。なにも言うつもりはないけれど、さすがに画像をそのまま、でリニューアルと言うのはどうだろう。とてもアンビヴァレンツな気持ちを持ちました。 |
 医者の話を聞いてみたり、ネットで調べたりしてみると、どうやら非特異性大腸炎という病名に落ち着くっぽい。非特異性とは、病原体が不明という意味であり、病原菌が明らかにされている腸結核、細菌性赤痢などの特異性疾患と区別されるらしい。現在の所の確定診断は直腸炎で、血液検査の結果では白血球が多く、全体に炎症が広がっている可能性があり、直腸の炎症だけではないみたい。ただ、直腸の組織片を採取して(物理的にへんな棒でぶちっと音をたてながら腸の一部をぶんどる。痛みはないけど音と振動でかなりへこむ。)分析した結果、組織学的には潰瘍性大腸炎ではないとのこと。報告書には Ulcerative colitis と英文でしか書かれてなかったのはなぜ? 油ものがダメっぽいにも関わらず昨日思いっきりマクドナルドでホットアップル
医者の話を聞いてみたり、ネットで調べたりしてみると、どうやら非特異性大腸炎という病名に落ち着くっぽい。非特異性とは、病原体が不明という意味であり、病原菌が明らかにされている腸結核、細菌性赤痢などの特異性疾患と区別されるらしい。現在の所の確定診断は直腸炎で、血液検査の結果では白血球が多く、全体に炎症が広がっている可能性があり、直腸の炎症だけではないみたい。ただ、直腸の組織片を採取して(物理的にへんな棒でぶちっと音をたてながら腸の一部をぶんどる。痛みはないけど音と振動でかなりへこむ。)分析した結果、組織学的には潰瘍性大腸炎ではないとのこと。報告書には Ulcerative colitis と英文でしか書かれてなかったのはなぜ? 油ものがダメっぽいにも関わらず昨日思いっきりマクドナルドでホットアップル パイ、ベーコンポテトパイ、チキンマックナゲットを食す。おかげで今日の具合は最悪。薬は整腸作用のある乳酸菌の乾燥粉末(だと思われる)ラクトン末と大腸の炎症を抑えるサラゾピリン錠を飲んでる。ほかにピロリ菌の繁殖を抑える効果があるとかいう明治プロビオヨーグルトをせっせと食べたりしてる。11月上旬に胃痛があったりしてたし。一昨日一度具合よくなったんだけど、しばらくは出血が続きそう。げそ…。
パイ、ベーコンポテトパイ、チキンマックナゲットを食す。おかげで今日の具合は最悪。薬は整腸作用のある乳酸菌の乾燥粉末(だと思われる)ラクトン末と大腸の炎症を抑えるサラゾピリン錠を飲んでる。ほかにピロリ菌の繁殖を抑える効果があるとかいう明治プロビオヨーグルトをせっせと食べたりしてる。11月上旬に胃痛があったりしてたし。一昨日一度具合よくなったんだけど、しばらくは出血が続きそう。げそ…。
 V6の岡田と三宅を見た。見たというか、目が悪すぎて実はよくわからなかった…。「学校へ行こう」の収録だったみたい。芸能人を見たのは久しぶり。眼鏡がないとつらいなぁ。意外に騒いでる人がほとんどいなくて、みんなまったりと見ていたのが結構驚きだった。通行人のひとりが電話で誰かに伝えているのが大げさに見えたほど。
V6の岡田と三宅を見た。見たというか、目が悪すぎて実はよくわからなかった…。「学校へ行こう」の収録だったみたい。芸能人を見たのは久しぶり。眼鏡がないとつらいなぁ。意外に騒いでる人がほとんどいなくて、みんなまったりと見ていたのが結構驚きだった。通行人のひとりが電話で誰かに伝えているのが大げさに見えたほど。 宝島社文庫 714
宝島社文庫 714